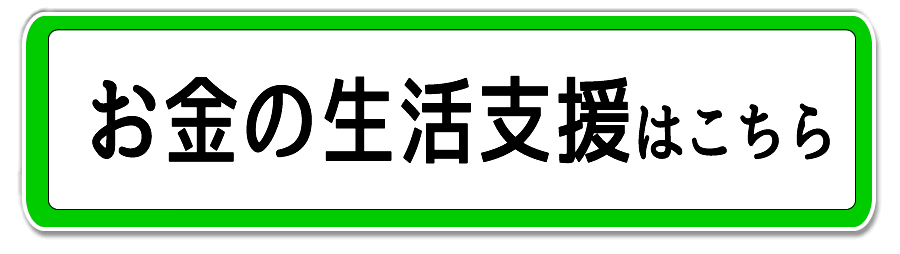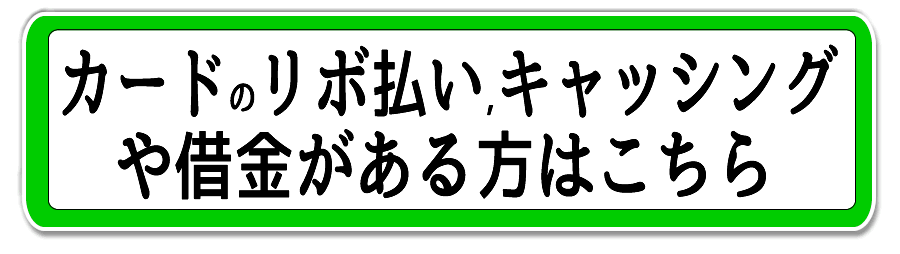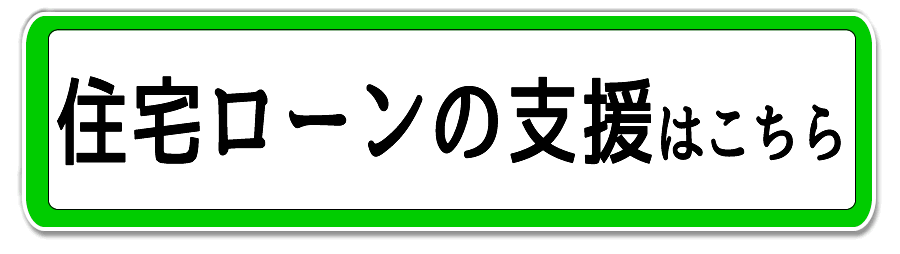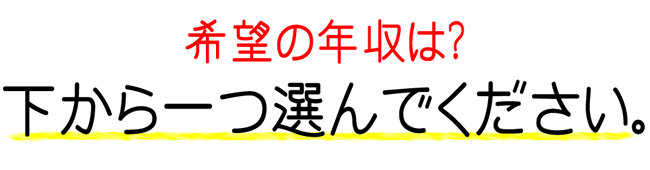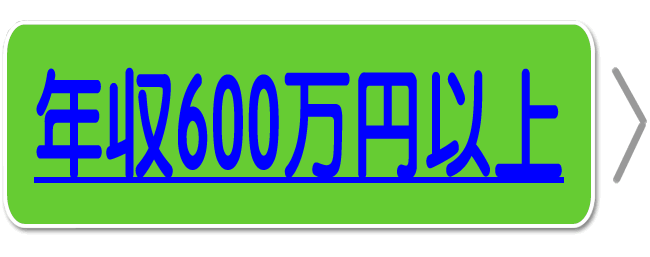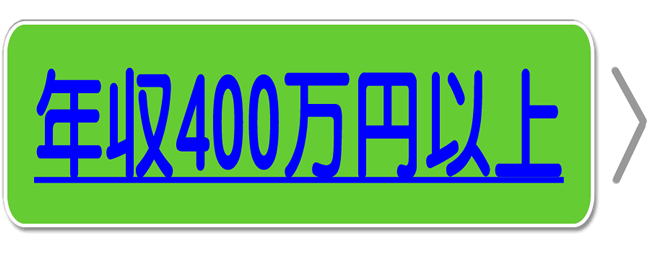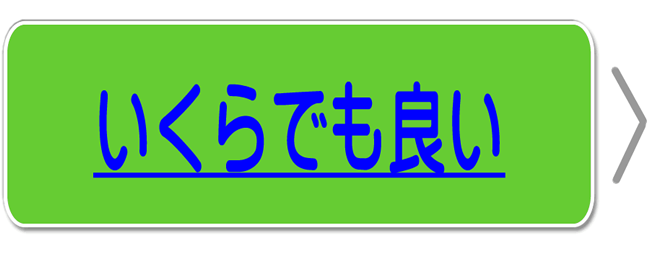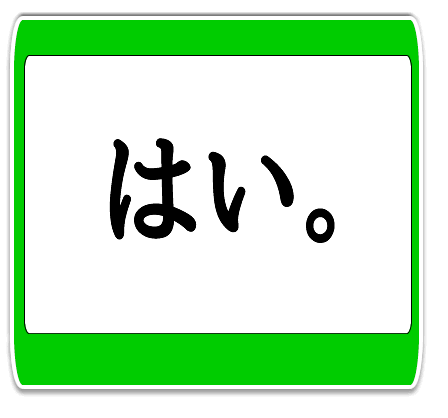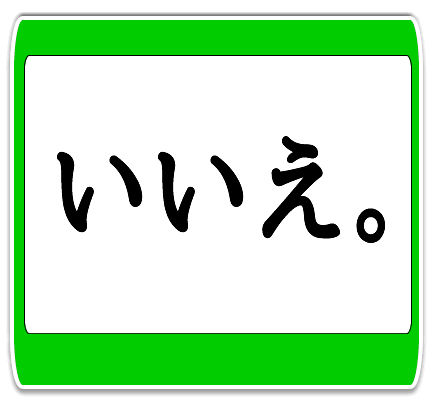関市で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう
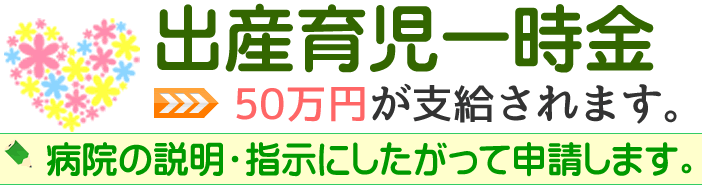

条件の良い仕事を探したい方はこちら
出産育児一時金とは?関市ではいくらもらえる?
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として50万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度とは?
出産に必要な費用が直接医療機関等へ払われる制度になります。
この制度によって出産に必要な費用を一時的に立て替えなくてよくなります。
出産費用が50万円に達しないときは、差額を支給申請することで、後から支払われますが、関市でも請求がないと受け取れないため気をつける必要があります。
出産育児一時金の他にもらえる出産手当金とは?
出産手当金というのは関市でおもに仕事をしている母親が妊娠している際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
関市で出産手当金の金額は?
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
関市の出産情報
関市でも、会社に雇用されていて雇用保険に加入中の人が、流産等、出産以前になんらかのトラブルが発生して会社を休業することになったときについて、出産の42日前なら出産手当金を受給できますが、それらの対象にならない場合は傷病手当金を受給できます。いずれについても休暇を取得した分の給与の三分の二が健康保険から出ますが、両方をもらうことはできないです。ダブった場合は、出産手当が優先になります。勤め先から休みの間も給与を貰っている場合では、減額されます。
お産のための代金がどれくらい必要であるかが気になるという人は関市でもたくさんいます。一般的な自然分娩は三十万から七十五万円と医療機関のあいだで開きがあるので、事前にリサーチしてから医院を決めるのがおすすめです。デラックスな個室等が整っている医療機関は代金が100万円超えの所もあります。さらに、お産が深夜等になってしまった場合は時間外料金が発生する所も多いです。初めてのお産のときに費用が追加されるところもあるみたいです。
関市のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら
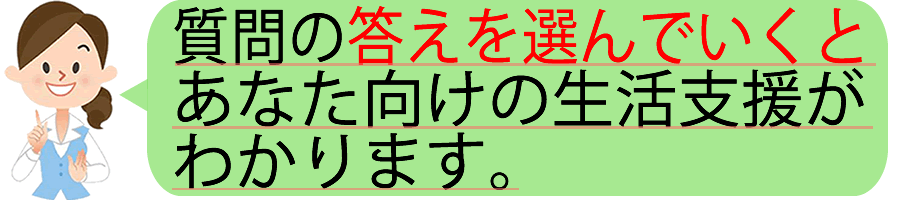

↑まずは選択してください↑
関市の街情報
| 遠藤内科 | 関市東福野町5-20 | 0575222286 |
|---|---|---|
| 長村医院 | 関市東山27-7 | 0575245281 |
| 耳鼻咽喉科・アレルギー科さいとうクリニック | 関市明生町5-1-39 | 0575251572 |
| 下條内科クリニック | 関市仲町6-13 | 0575225898 |
| 関市国民健康保険上之保出張診療所 | 関市上之保15082 | 0575472066 |
| にしだ泌尿器科クリニック | 関市緑町2-1-10 | 0575-25-2755 |
- 恵那市
- 瑞浪市
- 各務原市
- 揖斐郡池田町
- 土岐市
- 羽島郡岐南町
- 本巣市
- 羽島市
- 大垣市
- 高山市
- 羽島郡笠松町
- 中津川市
- 美濃加茂市
- 瑞穂市
- 岐阜市
- 多治見市
- 関市
- 本巣郡北方町
- 可児市
- 揖斐郡大野町
- 不破郡垂井町
- 郡上市

条件の良い仕事を探したい方はこちら
関市の生活支援
児童扶養手当だけではなく、経済的な援助を受けることができる公的制度が関市には設けられています。たとえば、夫が死亡してしまってシングルマザーになってしまったケースでは遺族基礎年金を受給できます。加えて、離婚などで片親になってしまったときにも年金等を払えないときは、支払額の全体や半分の金額の免除を受けることもできますので、支払えないときは減免をうけられるかどうか、市町村の役場に聞いてみることをオススメします。他にも、片親家庭の医療費を部分的に補助してもらえる制度も用意されています。
シングルマザーを補助してくれる手当として児童扶養手当があります。離婚や死亡等の理由で一人親により養われている児童の毎日の生活をを助けることを目的とした補助です。受け取れるのは、父母が離婚しているケースや、父母のいずれかを亡くしたり、または重度の障害を抱えている場合等です。結婚していない母親の子どもについても受給の対象となります。関市など、役場にて申請します。再婚したり、福祉施設等や里親に育てられている時は受給対象となりません。