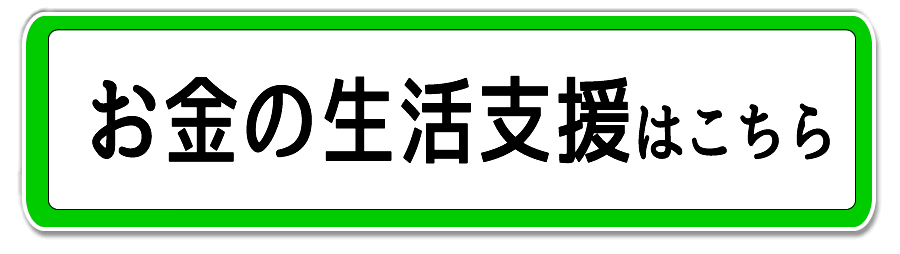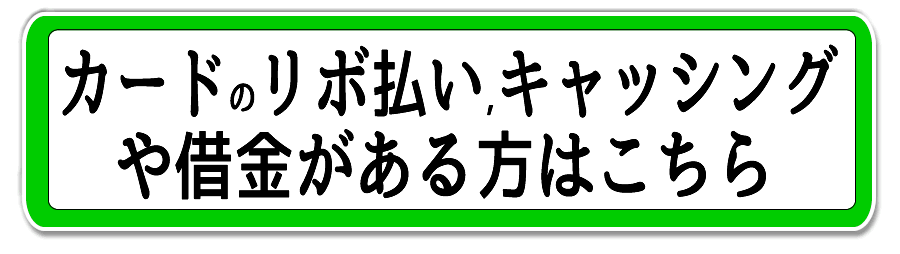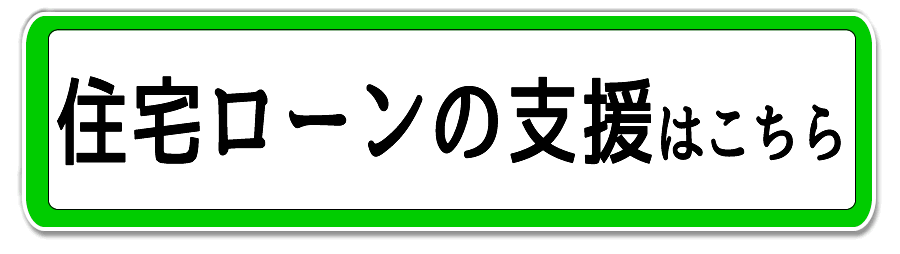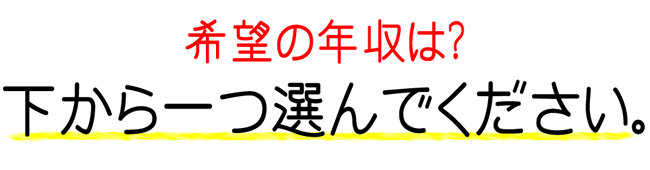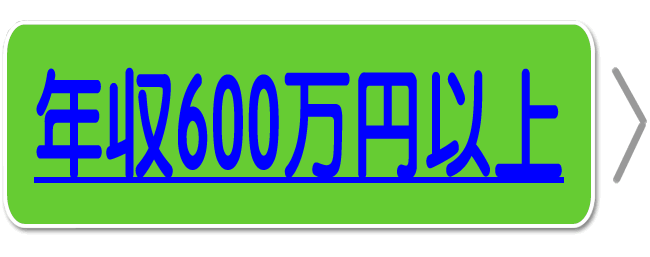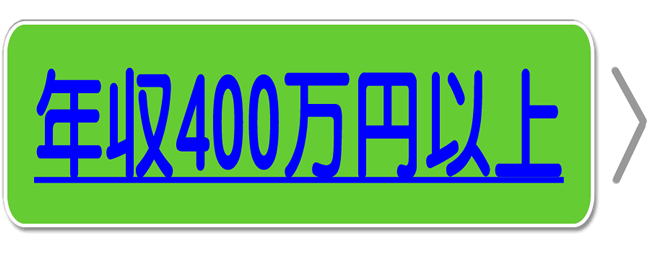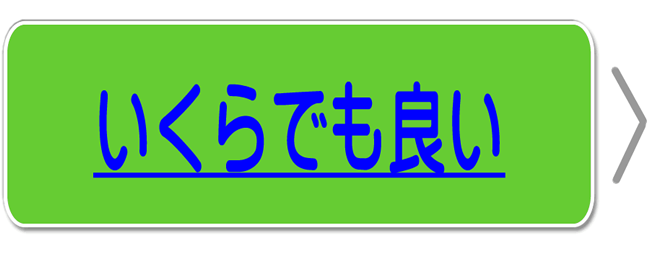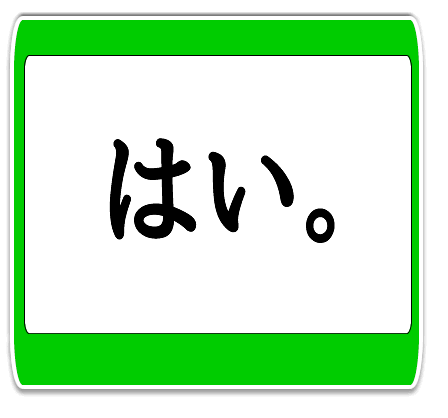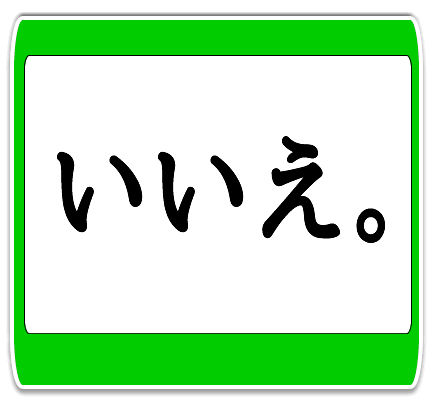山形県で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう
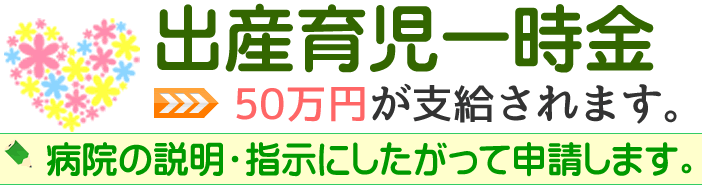

条件の良い仕事を探したい方はこちら
出産育児一時金とは?山形県ではいくらもらえる?
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度とは?
出産のための費用が直接病院などの医療機関へ払われる制度です。
この制度を使うことで出産のための費用を一時的に立て替える必要がなくなります。
出産に必要な費用が50万円かからなかったときは、差額分を申請することで、後ほど支給されますが、山形県でも申請しなければ支給されないため気をつける必要があります。
出産育児一時金以外にもらえる出産手当金とは?
出産手当金は山形県で主に働いている母親が妊娠している時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金が給付されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
山形県で出産手当金はいくらもらえる?
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった日数です。
山形県の出産情報
なんらかの事情にて片親家庭になる方が赤ちゃんを産んで子育てをしていく場合、その生活を応援するために児童手当のほかにも児童扶養手当というものが山形県でも設けられています。離婚などの事情により片親家庭になった子どものための制度で、十八歳になったあとの三月末になるまで支払われます。年収によって最高一月に4万円ほどをもらうことが可能ですが、手続きをしないと受給することができませんので注意を払うことが必要になります。申込みは市町村の役場にてできますので、間違いなくやりましょう。
山形県でも、仕事をしていて雇用保険に加入中の人が、切迫流産など、お産前になにかのトラブルを患って勤めを休みを取得する事になる場合について、お産の四十二日以前ならば出産手当を受け取れますが、対象外のときは傷病手当金を受給することができます。いずれについても休業した日数分の賃金の3分の2が健康保険から貰えますが、両方とも受けとることはできないです。二重になった時は、出産手当が支払われます。勤務先より休業している期間も賃金を貰っている場合については少なくされます。
山形県のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら
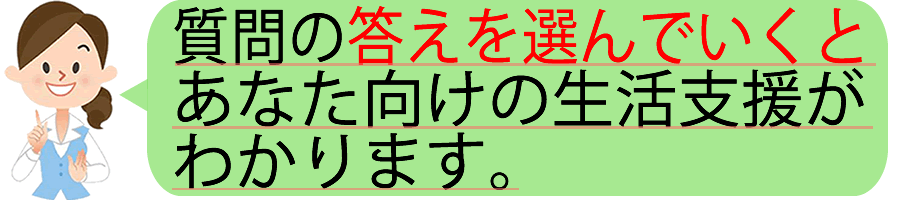

↑まずは選択してください↑
山形県の街情報
| たかだ内科 | 米沢市万世町金谷666 | 0238-26-9337 |
|---|---|---|
| わだ内科医院 | 鶴岡市下川七窪2ー1198 | 0235-76-0011 |
| 梅津医院 | 長井市大町2ー27 | 0238-88-2078 |
| みかわキッズクリニック | 東田川郡三川町猪子字大堰端379ー7 | 0235-35-0666 |
| 医療法人渡辺医院 | 東根市大字羽入2821 | 0237-47-0406 |
| 江部耳鼻咽喉科医院 | 酒田市新井田町1ー37 | 0234-24-3387 |

条件の良い仕事を探したい方はこちら
山形県の生活支援
母子家庭や父子家庭を支えてくれる手当には児童扶養手当が用意されています。シングルマザーの子の生活を支援する制度で、山形県等、現在住んでいる窓口で申し込めば払われます。普通は月ごとに4万ほどがもらえますが、申し出ないと払われないので、届け出ていない方は、きちんと申し出るようにしましょう。子どもが18歳の誕生日を迎えて次の三月三十一日をむかえるまで払われ、児童手当等と同じく子に支払われる助成金です。日々の暮らしを営んでいくために、子どもの環境を整える助成金になります。
母子家庭という言葉は山形県では社会的にも知られていますが、父子家庭については、ほとんど浸透していません。実情として、前は児童扶養手当については母子家庭の子どもだけに払われて、父子家庭には支払われませんでしたが、平成22年より、父子家庭についても受給できるように法律が改正されました。子どもが小さい場合は母親が親権を持つケースが通常なため父子家庭というのは多数派でなかったり、生活に十分な職業に就いているケースが多かったので、対象外にされてきましたが、シングルマザーのみでなく、父子家庭についても補助が必要であるということが認定されたということです。