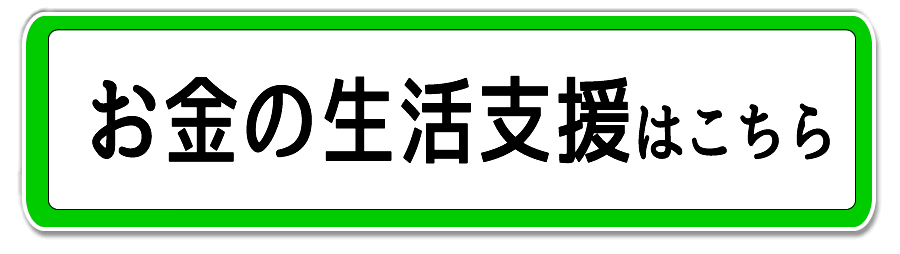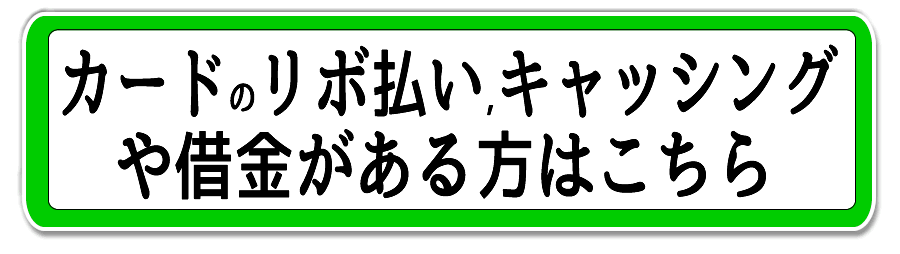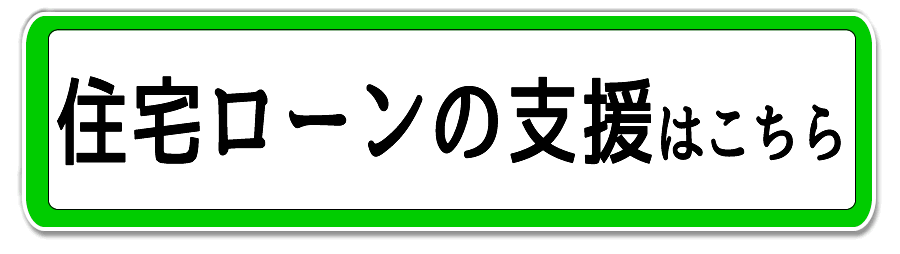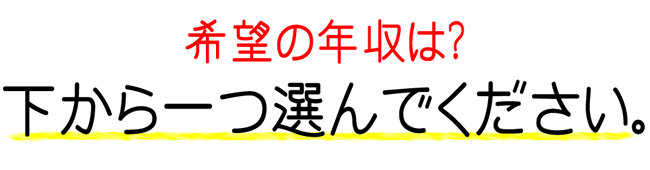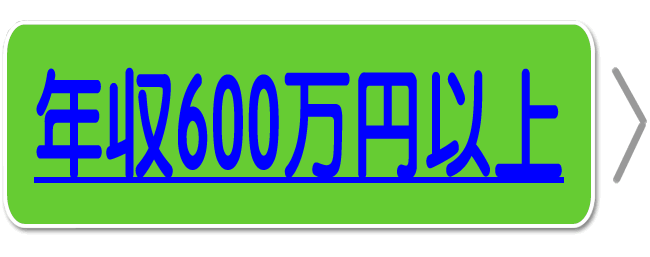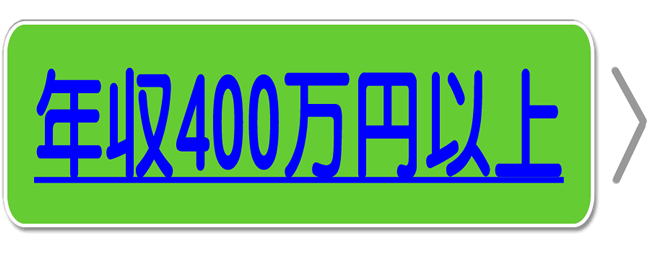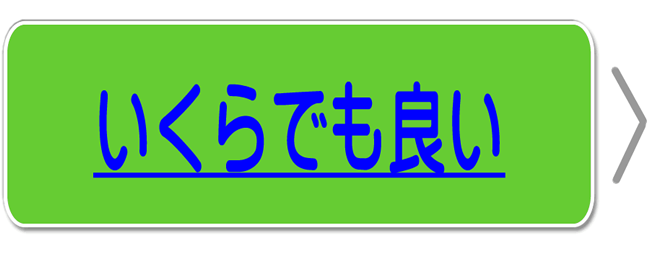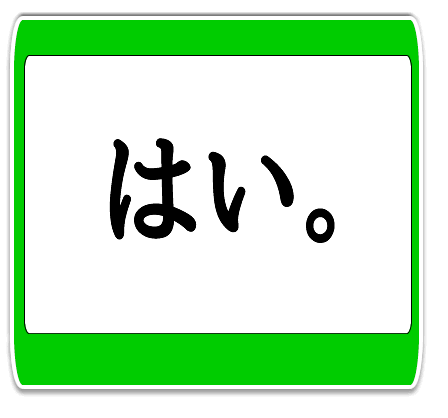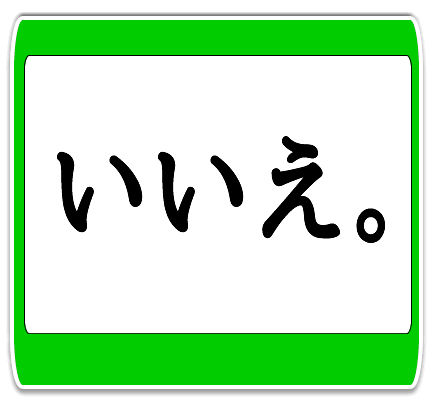宇城市で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう
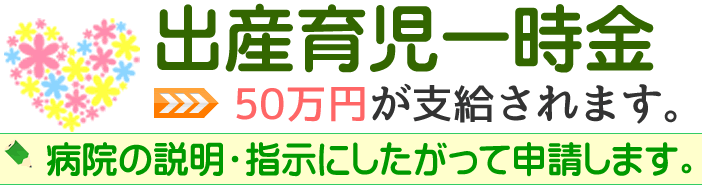

条件の良い仕事を探したい方はこちら
出産育児一時金って何?宇城市ではいくらもらえる?
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として50万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度とは?
出産に必要な費用が直接病院などの医療機関に払われる制度です。
この制度を使えば出産のための費用をいったん立て替えることがなくなります。
出産時の費用が50万円もかからなかったときは、差額について申請することで、後ほど受け取れますが、宇城市でも請求しないと受給できないため注意が必要です。
出産育児一時金とは別にもらえる出産手当金とは?
出産手当金というのは宇城市でおもに就業者である女性が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
宇城市で出産手当金はいくらもらえる?
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
宇城市の出産情報
出産のための料金については健康保険の対象外なため全額自分で負担して払わなければなりませんが、健康保険に自分または夫が入っていれば出産育児一時金として子供1人あたり50万円をもらえます。一昔前は、退院の時に出産による代金を支払っておいて、あとで出産育児一時金を支給してもらうということも宇城市では少なくなかったのですが、今は、直接支払い制度が当たり前ですので医院の精算での代金を払う時には、50万円との差額を支払う事が大部分になります。料金が50万と比較して安かった場合は、後に差額分をもらえます。
働いている人の中にはお産寸前まで働きたいといった人が宇城市でも少なくないです。原則出産以前の42日の間と出産後の五十六日の間は休業する権利が保障され、休暇をとった時は出産手当として休暇をとった日数の給与の2/3が健康保険より受け取れます。この期間中についても会社と医者が認めれば勤務することも可能ですが、お産を終えた後の42日のあいだは規則上仕事をすることはできません。身体を大事にしつつ、出産手当金の援助に頼っていくこととなります。
宇城市のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら
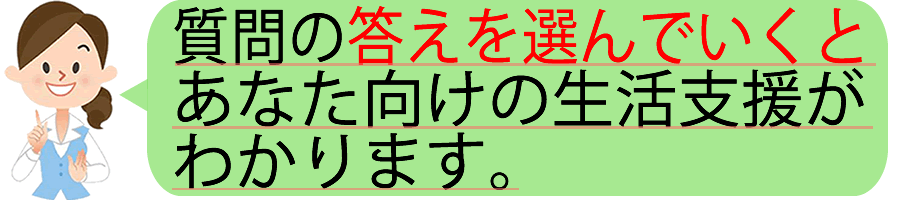

↑まずは選択してください↑
宇城市の街情報
| 国民健康保険宇城市民病院 | 宇城市松橋町豊福505 | 0964-32-0335 |
|---|---|---|
| 中村医院 | 宇城市松橋町砂川1729-2 | 0964-32-0722 |
| しまだこどもクリニック | 宇城市松橋町きらら三丁目2番19号 | 0964-34-3933 |
| 本田医院 | 宇城市松橋町南豊崎585 | 0964-32-0555 |
| 狩場医院 | 宇城市豊野町糸石3897 | 0964-45-2017 |
| 佐藤医院 | 宇城市三角町戸馳1680 | 0964-52-2748 |

条件の良い仕事を探したい方はこちら
宇城市の生活支援
シングルマザーということばは宇城市では自然に用いられていますが、父子家庭については、それほど用いられません。現実に昔は児童扶養手当はシングルマザーの子どもだけが対象で、父子家庭には支給されませんでしたが、平成二十二年より、父子家庭も対象になるように法改正されました。子供が低年齢の際には母親が親権を持つという決定になるケースが一般的なため父子家庭というのは数が少なかったり、父側というのは収入になる職業に就いているケースが大部分だったので、支払われませんでしたが、シングルマザーのみでなく、父子家庭も支えが必要と理解されたわけです。
シングルマザーを助けてくれる手当てには児童扶養手当が提供されています。シングルマザーの児童の人生の援助をしてくれる制度で、宇城市等、各窓口で申し出ることで受け取れます。通常は月当たり40000位が支払われますが、申請しないと支払われないので、届けていない場合は、きちっと申請するようにして下さい。子どもが十八才になって最初の三月末になるまで支払われ、児童手当等と同様に子供に対して支払われるシステムです。日々の暮らしを維持するために、子どもの環境を整える補助になります。