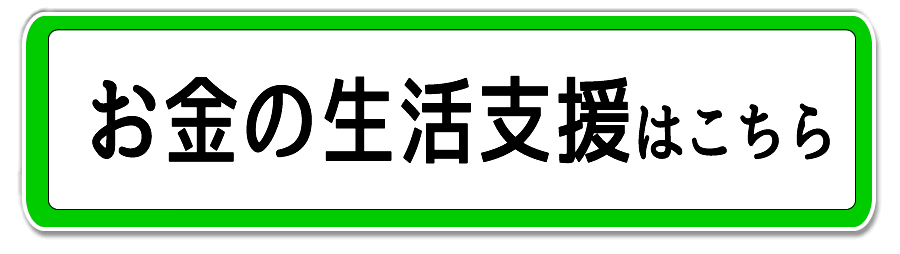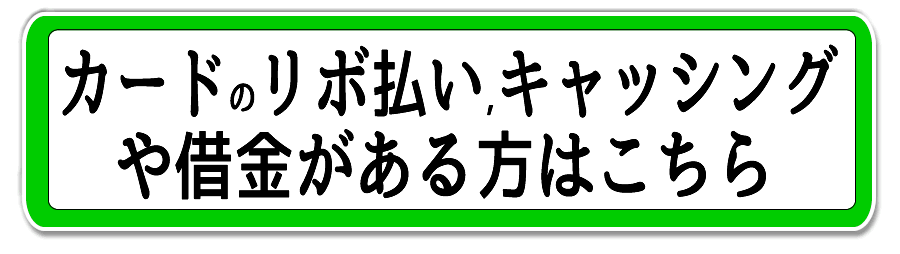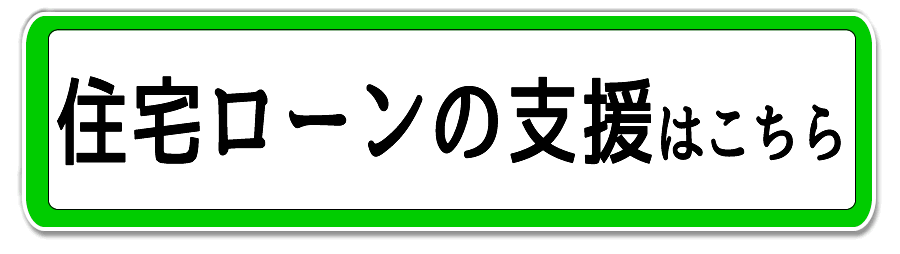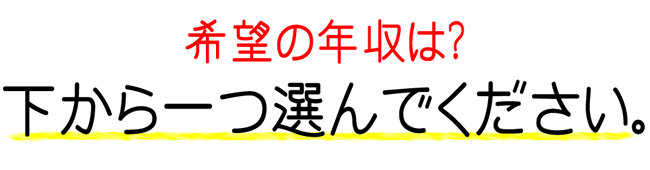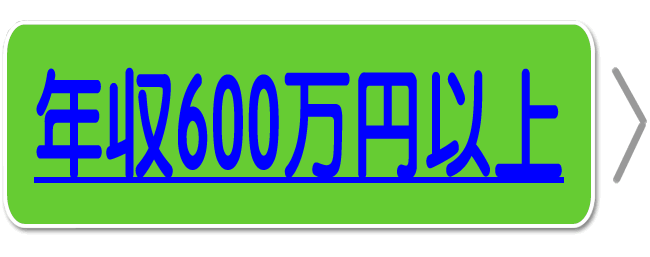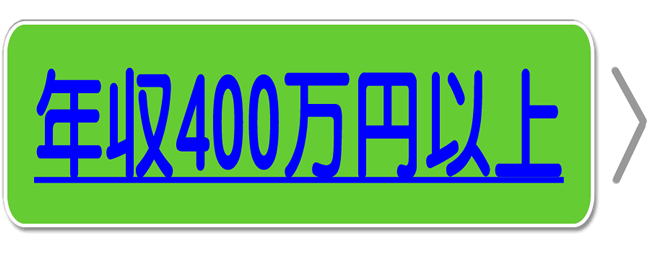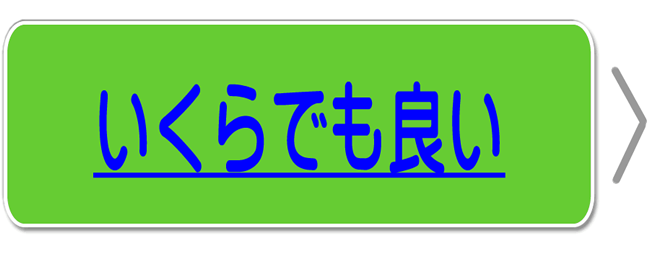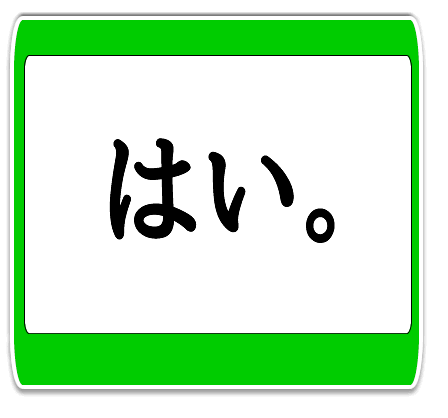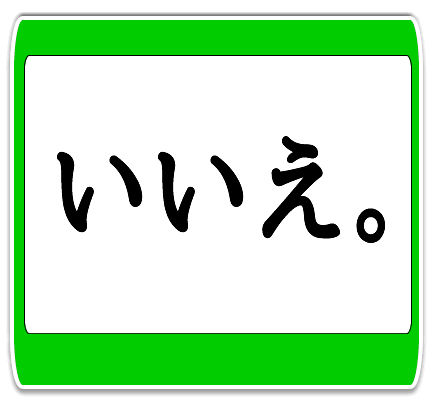津山市で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう
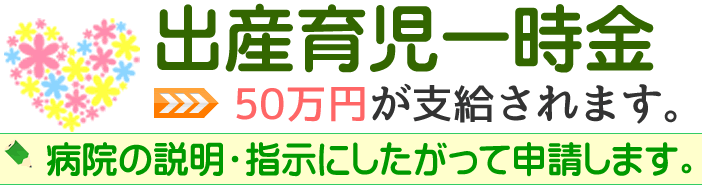

条件の良い仕事を探したい方はこちら
出産育児一時金とは?津山市ではいくらもらえる?
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度とは?
出産にかかる費用が直接病院などの医療機関へ払われる制度です。
この制度により出産にかかる費用を一時的に立て替えする必要がなくなります。
出産にかかる費用が50万円もかからなかったときは、差額について申請することにより、後日受け取れますが、津山市でも支給申請がないともらえないため注意が必要です。
出産育児一時金のほかにもらえる出産手当金とは?
出産手当金は津山市でおもに仕事をしている母親が出産するときに適用される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
津山市で出産手当金の金額はいくら?
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった日数になります。
津山市の出産情報
なんらかの事態にてシングルマザーになった方が出産して子育てをする時、その暮らしを応援するため児童手当以外にも児童扶養手当といった物が津山市でも提供されています。未婚の母などの事情によって母子家庭である子供の制度で、18歳になって最初の3月まで受け取ることが可能です。収入に応じて最高月額4万円程を支払われますが、申込みしないと受給することができませんので注意を払うことが必要です。手続きは市町村の役所でできるので忘れないでやりましょう。
自然分娩のお産は避けるべきと判断がなされたときは帝王切開での出産が選択されます。約20パーセント弱の方が帝王切開の出産となって、入院が一週から十四日ということでおよそ倍となって津山市でも入院にかかる代金は割高ですが、帝王切開手術料金については健康保険がつかえるため、すべての出産のための代金については50万から百万ということで自然分娩と変わらない額になってきます。お産の手段の差異よりも、病院のオプションや部屋のつくりなどの方が全ての代金に関係してきます。
津山市のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら
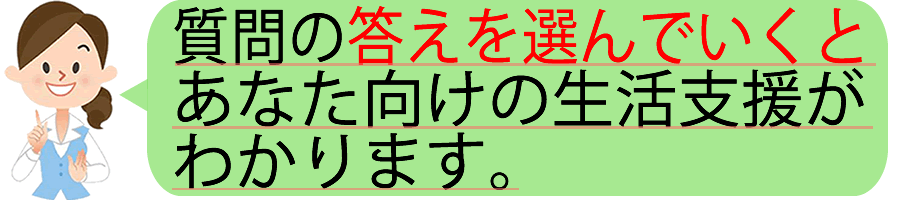

↑まずは選択してください↑
津山市の街情報
| 只友医院 | 津山市加茂町塔中105 | 0868-42-2043 |
|---|---|---|
| 三宅医院 | 津山市中北下1189ー4 | 0868-57-2037 |
| 医療法人 水島圭一内科医院 | 津山市沼52番地の10 | 0868-25-1212 |
| 上野眼科クリニック | 津山市山下9番地の5 | 0868-31-3911 |
| 財団法人江原積善会 積善病院 | 津山市一方140番地 | 0868-22-3166 |
| 水田皮膚科泌尿器科内科 | 津山市南新座105 | 0868-23-2108 |

条件の良い仕事を探したい方はこちら
津山市の生活支援
母子家庭として暮らしを営んでいくと、自分自身の給料の上がり下がりがじかに家計に響いてきます。時には、毎月の請求額の支払を前にして、すぐ現金がいるといった事もあると思います。そんな時につかわなくなったかばんなどを買取して現金にできる質屋の存在は役に立ちます。津山市にて、買取価格を少しでも高額にしたいといった際は、宅配買取を選ぶと高く売れます。携帯電話とネットで依頼すると自宅に届けられるダンボールに買い取ってもらいたいものを入れておくるだけで査定してもらえて、査定がOKの時は、振込みにて入金してもらえます。
母子家庭という単語は津山市ではふつうに知られていますが、父子家庭については、それほど使われていません。実情として、以前は児童扶養手当についてはシングルマザーの子どものみで、父子家庭は受給できませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭も支払われるように改定されました。子どもが小さいときは母親に親権が認められるケースが一般的なため父子家庭は多くなかったり、父側はある程度の職業に就いていることが多かったので、これまでは対象に入っていませんでしたが、母子家庭だけでなく、父子家庭についてもサポートが不可欠であると判断された結果です。