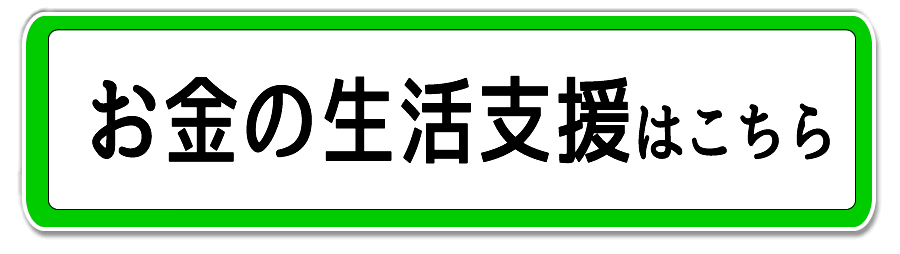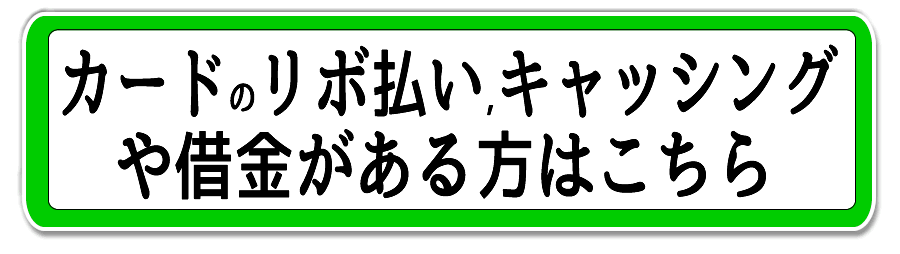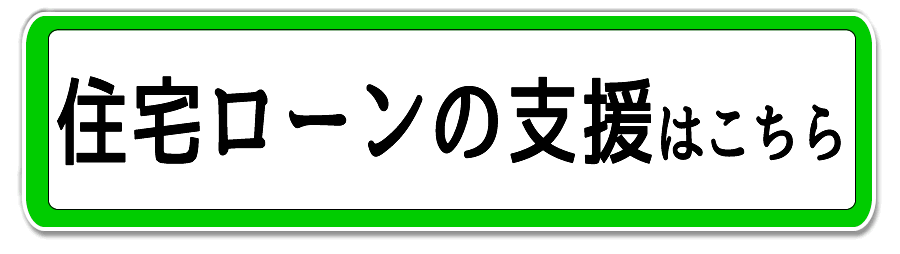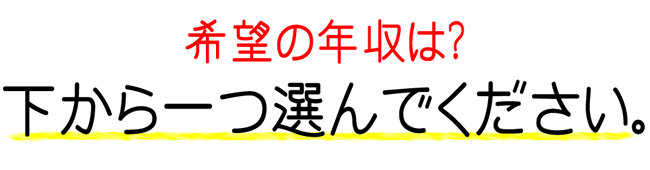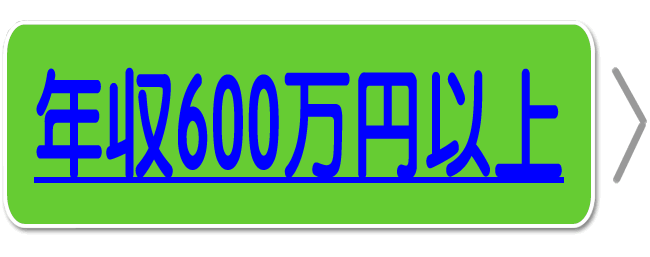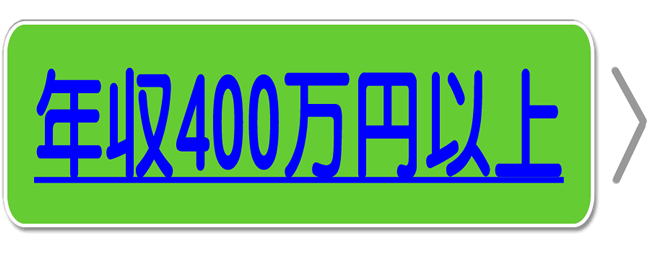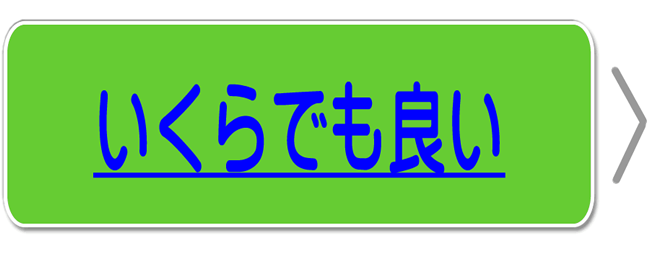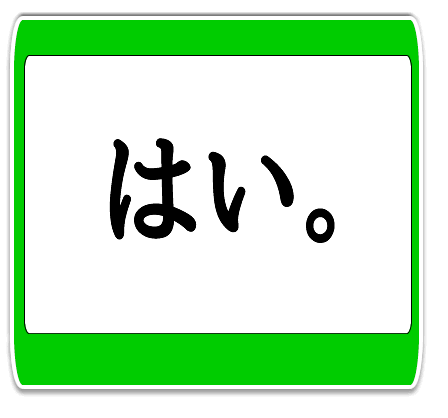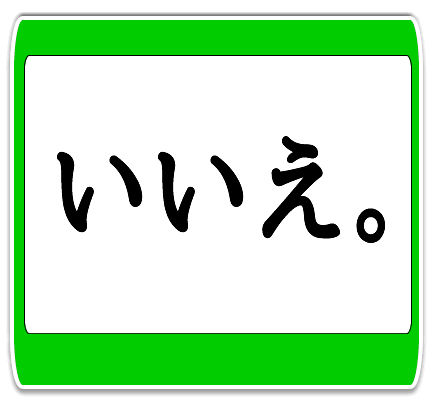長野県で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう
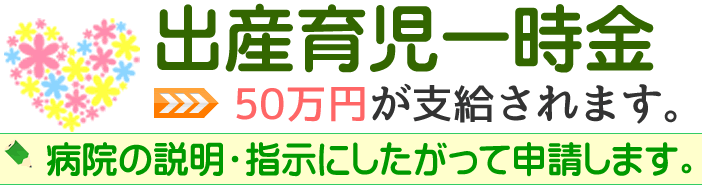

条件の良い仕事を探したい方はこちら
出産育児一時金とは?長野県ではいくらもらえる?
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として50万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産育児一時金の直接支払制度って何?
出産のための費用が直接医療機関などへ支払われる制度になります。
この制度を利用すれば出産に必要な費用を一時的に立て替えることがなくなります。
出産に必要な費用が50万円未満の場合は、差額について申請することによって、後でもらえますが、長野県でも支給申請しないと給付されないため気をつけましょう。
出産育児一時金のほかに受給できる出産手当金って何?
出産手当金というのは、長野県でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象です。
長野県で出産手当金はいくらもらえる?
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
長野県の出産情報
日本人と外国人の結婚の場合に出産育児一時金は受け取れるか否か気になってしまうというような方は長野県でも少なくないです。基本的に健康保険に入っているならば受け取れます。妻が日本人ではない時は、ご主人が加入中ならば受給できますし、奥様がが会社に勤めていれぱ雇用先の健康保険からもらえます。夫が日本人ではないときも、奥さんが会社に勤務していれぱ職場で加入している健康保険より受給できますし、専業主婦のときもご主人が健康保険に加入していれば出産育児一時金は払われます。
妊娠してお産するまでに体重が増えたという人は長野県でも多いです。とはいえ、妊娠時に増加した脂肪というのは流動性脂肪と言われてとりやすく、とりわけ出産して6ヶ月から十二ヶ月程度はやせやすい時になるので、この間に妊娠前の体重に戻すことが必要です。子供を産んで一ヶ月半位経過して体調が安定したら、食べ物の栄養バランスを取って軽いエクササイズをする様にダイエットを目指すのがオススメです。突然食事を抜いてしまったり、過度なエクササイズはやめたほうがいいですし、それまで無理しなくても減量はできます。毎日の生活習慣を健全化するようにしていくのがポイントです。
長野県のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら
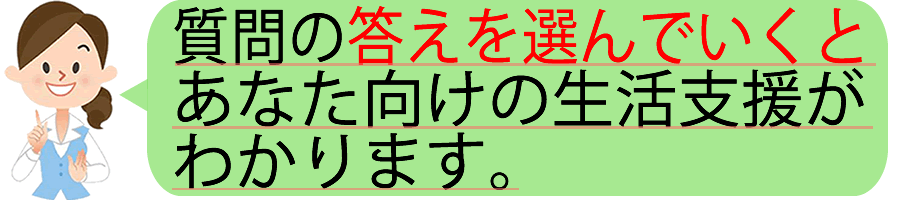

↑まずは選択してください↑
長野県の街情報
| 伊那市国保美和診療所 | 伊那市長谷非持564番地 | 0265-98-2017 |
|---|---|---|
| 倉科医院 | 松本市大手2-9-16 | 0263-32-4163 |
| 医療法人みすゞ会 星のさとクリニック 水野医院 | 長野市篠ノ井小松原2359―25 | 026-292-0191 |
| 片塩医院 | 飯山市南町22-10 | 0269-62-2136 |
| 長野市国民健康保険大岡診療所 | 長野市大岡乙254ー1 | 026-266-2310 |
| てらおかクリニック | 佐久市甲1062-2 | 0267-51-5222 |

条件の良い仕事を探したい方はこちら
長野県の生活支援
母子家庭という単語は長野県では一般的にも使用されていますが、父子家庭は、ほとんど使われません。現実問題として、ひと昔前は児童扶養手当はシングルマザーの児童のみに払われて、父子家庭は受給できませんでしたが、平成二十二年から、父子家庭についても対象となるように改定されました。子どもが幼い際には親権は母親に認められる場合がほとんどなので父子家庭というのは多数派でなかったり、収入になる職についている事が多数だったため、これまで対象からははずされていましたが、母子家庭にかぎらず、父子家庭についても援助が不可欠であるということが判断されたのです。
一人親世帯を助ける母子家庭手当てということで児童扶養手当が提供されています。シングルマザーの子供の毎日の暮らしをサポートする手当てで、長野県等、今住んでいる市町村の役所にて申し込めばもらうことができます。一般的には月額四万ほどが受け取ることができますが、届け出ないともらえないので、申請してないときは、きちんと申し込むようにしましょう。子どもが18歳になって次の三月末まで受け取れ、児童手当等のように子どものために設定されている手当てになります。日々の暮らしを維持をしていくために、子どもの発育環境を整える助成金になります。